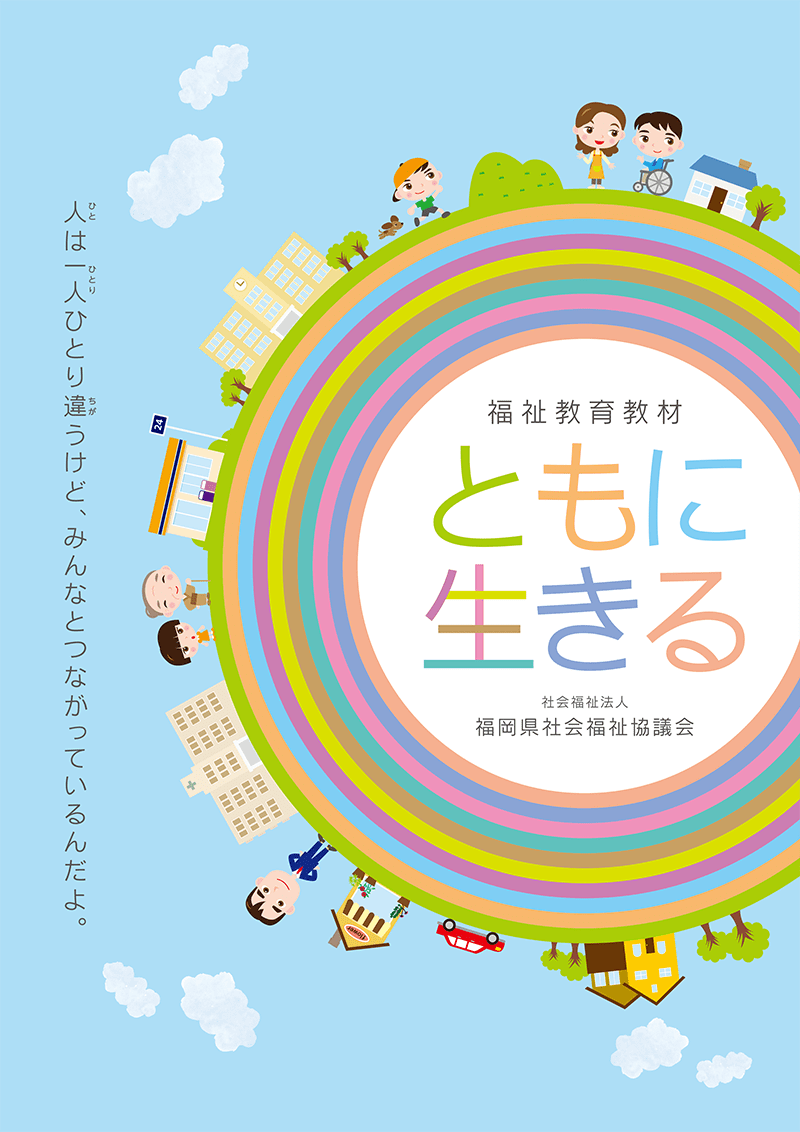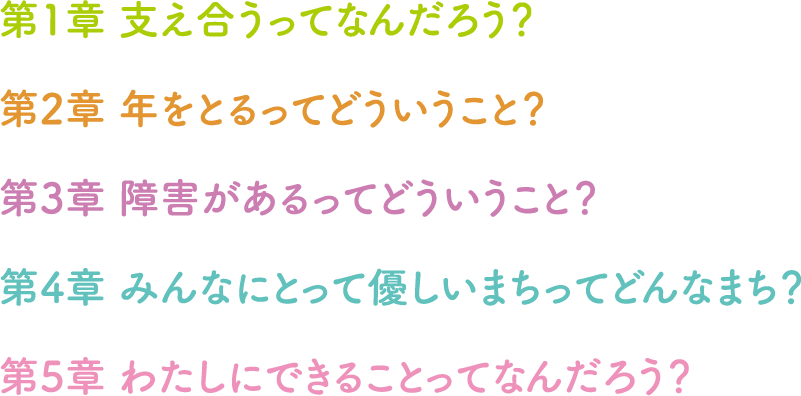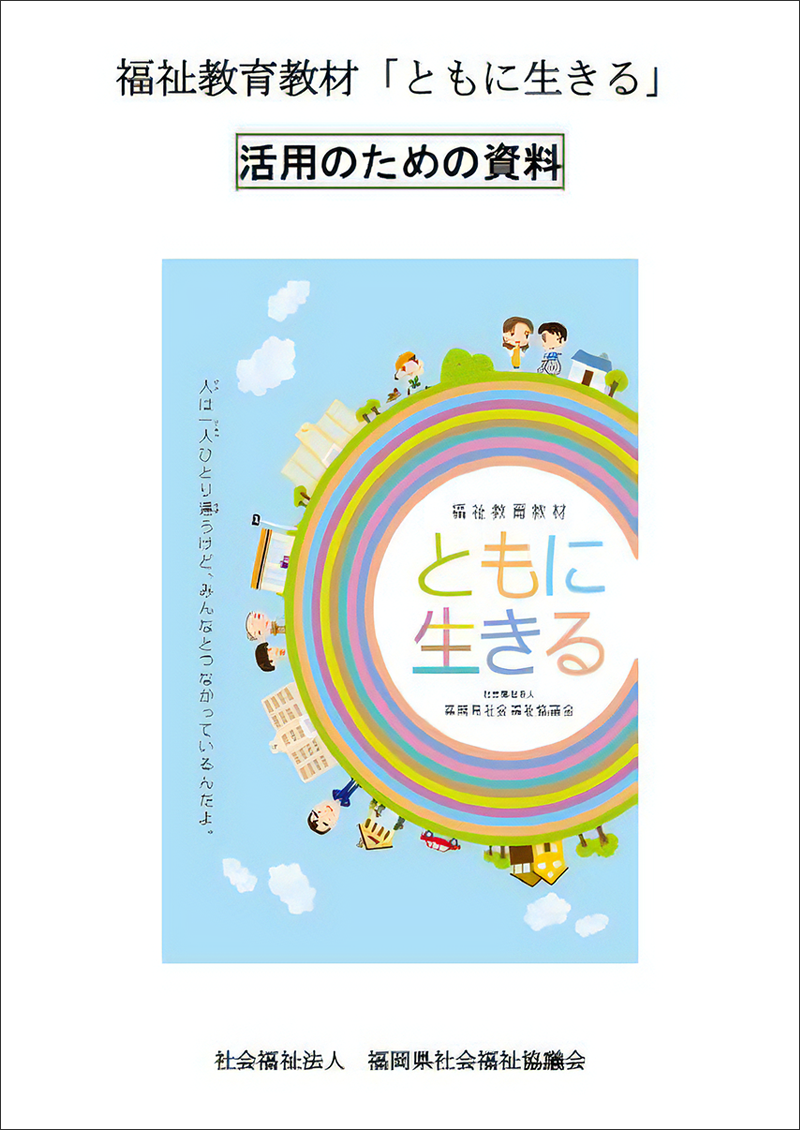福祉教育
県民の皆様へ - 地域福祉活動について
福祉教育とは
私たちの住む地域には様々な人がいます。その誰もが安心して楽しく豊かに住み続けられる「共生の地域づくり」を進めることが地域福祉の主要な目的であり、それを達成するために様々な福祉教育が実践されています。
福祉教育は、住民参加の地域福祉の基盤づくりに欠くことができないものであり、特に学齢期における福祉の心づくりは、ともに支え合う心豊かな地域社会の実現に向けて大きな基礎となります。
「思いやりの心をもって、ともに育ち、ともに生きるための福祉のこころを育む」ため、この取り組みを通して地域の様々な福祉課題を地域全体・住民全体で考え、取りんでいく力を育んでいくことが福祉教育には求められています。
福祉教育教材「ともに生きる」
本会では、福岡県・北九州市・福岡市の各教育委員会や学校関係者等の協力を得、平成26年度に福祉教育教材「ともに生きる」を発行し、学校・社会福祉協議会・地域が協働した福祉教育の推進に積極的に取り組んでいるところです。
第1章 支え合うってなんだろう?(PDF)
第2章 年をとるってどういうこと?(PDF)
第3章 障害があるってどういうこと?(PDF)
第4章 みんなにとって優しいまちってどんなまち?(PDF)
第5章 わたしにできることってなんだろう?(PDF)
福祉教育教材「ともに生きる」活用
本会では、福祉教育教材「ともに生きる」の活用の推進を図るため、章ごとの「学習活動例」、「指導上の留意点」をまとめた活用のための資料を発行しております。
福祉教育教材「ともに生きる」とともに一体的にご活用いただき、学校、社協、福祉施設、地域が連携した新たな福祉教育の展開の一助としていただければ幸いです。
地域における福祉教育を推進するため、福岡県福祉教育プログラム策定委員会を設置し、学校、社協、地域が連携した福祉教育を県下に広げる一環として、社会福祉協議会の職員から地域住民、団体、ボランティア、学校などに対し福祉教育をより理解していただくための参考資料として、「福祉教育教材「ともに生きる」活用のための資料」「学校向け福祉教育パンフレット」「福岡県版福祉教育教材「ともに生きる」を活用した学校、社協、福祉施設、地域ですすめる福祉教育プログラム集」を発行いたしました。
福祉教育をすすめるための基本方針
少子高齢・人口減少が進行する中、地域生活課題は多様化、複雑化し、近年は、貧困や虐待、いじめ、不登校など、子どもを取り巻く家族や学校の課題も重層化しています。
このような中、地域の未来を担う子どもたちが自ら考え、思いやりの心を持って行動する力を育むことに加えて、多様な人が居住する地域において、ともに学びあう機会をつくり、「福祉のまちづくり」を進めるための福祉教育の必要性は高まっています。
各市町村における福祉教育の推進のためには、市町村社会福祉協議会(以下、「社協」)の福祉教育担当者をはじめ、全ての職員が今日的な福祉教育の理論の共通理解を図るとともに社協間連携の基盤づくりが不可欠です。
そこで、多機関が連携し、社協がその中心となって福祉教育を推進するために、県内において、社協、学校、地域、社会福祉施設等、福祉教育を推進する者同士が共通の認識を持って取り組むための考え方、手法を示すため、基本方針を策定しました。
問い合わせ先
地域福祉部 地域・ボランティアセンター
FAX 092-584-3369